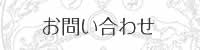マンスリーゾディアック
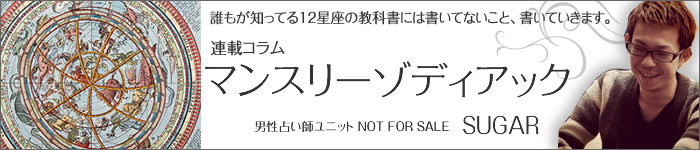
マンスリーゾディアックとは 日本語で言えば「毎月の12星座」です。
太陽の通り道「黄道」 そこには12個の星座が配置させていおり、毎月30度ずつ進んでおります。それを「黄道12宮」と言います。
そこの場所を太陽が通過するとき、「○○座」という表現になります。 (私の誕生日は○○座) マンスリーゾディアックでは毎月の太陽星座を見つつ、その星座に隠れている「教科書には書かれていない星座の事」をピックアップしてまいります。 どうぞお楽しみに☆
第9回【射手座について】
NOT FOR SALE Sugar
■射手座は根深い思い込みから脱獄する
射手座は一般的に「楽観的で哲学的」と書かれていることが多い星座です。そう言われると、なんとなく、ああそういうものかと思って流してしまいがちですが、よくよく考えてみると、ちょっと小首を傾げたくなる文言の並びではありませんか?だって「哲学」って、なにか深遠な世界観だとか、含蓄ある人生論なんかを、厳格な論理の格子で編んで、そこに緻密に言葉を詰め込んでいくことで長大な思想体系(哲学の塔)を構築するような、少なくとも、とても一筋縄にはいかないイメージのはず。そんな面倒そうなものの傍らで、「楽観的」という言葉から連想される膨張的でバブル景気のような空気感を、人は果たして纏うことができるのだろうかと。悩ましげに俯きつつ眉間にしわを寄せる「考える人」のような、どこか物憂げで哀しみを秘めた雰囲気と、恐れを知らぬ過剰さで自らを肯定する愉悦と開放的な空気感。その両者が一人の人間、一つのイメージの中に両立しえるというのは、少し考えても奇妙という他ないでしょう。その不可思議は、神話が伝える射手座のモデル、ケンタウロス族の長・ケイローンの、下半身が馬で、上半身が人間という特異な姿にも重ねることができるかも知れません。全天でもっとも古い起源をもち、12星座唯一の人獣一体、あるいは最も際立った異質混淆の星座である射手座は、何ゆえそのような奇妙さ・不可思議さを体現して在るのか?差し当たってはまずこの違和感を縦糸にしつつ、以下歩を進めていきたいと思います。
9番目の星座である射手座は、牡羊座と獅子座に続く3番目にして最後の「火の星座」でもあります。火は12星座において、さながらオリンピックの開幕を象徴する聖火ランナーのように、つねに「新しい経験領域をもたらす案内役」を担うエレメントですが(星座は四元素で見ていくと必ず火→地→風→水の順で並んでいる)、3番目の火からは一体なにが始まっているのでしょうか?(あるいは、1番目の個人的な領域、2番目の関係性の領域に次いで、3番目の4星座は、公的でトランスパーソナルな経験領域を表していると言われるのは一体なぜなのか)。こうした問いに答えるためには、まずケイローンによって引き絞られた矢が蠍座の心臓・アンタレスに向けられているという点に着目していく必要があります。
じつは、蠍と射手には古くから深い結びつきが見られ、紀元前13世紀のバビロニア時代の石碑には、ケイローンの下半身は馬ではなく蠍となっており、全体は羽をはやした蠍人間として描かれていますし、世界最古の神話であるメソポタミア神話には「蠍の尾」をもつ半人半馬の合成獣が登場し、これがケンタウロスの原型でもあります(『ギルガメッシュ叙事詩』)。つまり、射手座のモデルというのはその原型において蠍座のモデルと未分化の状態で融合していた訳で、これは象徴的に、蠍座の本質から射手座のそれへと完全に移行しきるということが、いかに大変なことなことであるかを示しているのだとも言えるでしょう。
前回書いたように、蠍座には「(他者との)終わりなき闘争」を終息させるため、孤独感や渇きをもたらす二項対立(わたしとあなた、見るものと見られるもの、意識と無意識、光と闇etc)を、わが身の内部に溶かし込むことによって破棄し、無効化する(「ろ過」)という役割がありました。そしてその役目を果たすため、蠍はごく自然に深海の氷山、火山の底といった、空間の“深み”へと身を置いた訳ですが、それゆえにある種の限界をも抱えていました。というのも、人間の想像力が深さという方向をとるとき、そこには必ず、かたちを宿す実体、つまり現象の背後にあってその現象を支配し、内側から現象を動かす見えざる何か(力や価値)を伴わざるを得ないからです。蠍は英雄オリオンをその毒針で殺したことで有名ですが、その背後には自分にかなう動物などいないと広言してみせたオリオンの傲慢さに怒り、蠍を差し向けた地母神ガイアという張本人(実体)が存在します。つまり、暗黒の門としての死をあつらえたのはあくまでガイアなのであって、蠍はそのおとないを告げ、本当の実体が憑依する依り代に過ぎないんです。これは言い換えれば、蠍座の心臓アンタレスー火星(アレス)に抗(アンチ)するもの―とは、蠍を使役する実体としてのガイアなのだということですね。
ガイアは大地を象徴する女神ですが、それは本来、天をも内包するこの世界=地球のことであり、文字通りに大地のみを指す訳ではありません。そんな「この世そのもの」であるガイアと蠍との間にみられる絶対的な被支配関係こそが、“つながり”によって生きる「水の星座」である蠍座の深みの底に沈んでいた鉄鎖のごとき本質でもあったんです。それは、父も母も存在する前から世代を超えて受け継がれ、自らもまた繋いでいく「いのちの連鎖」であると同時に、いのちは必ず他のいのちの犠牲の上に成り立っているという生物世界の相互依存的な実相を支える「食物連鎖」の掟でもありました。人間というのは生存することによって必ず誰かを殺しており、それゆえ、いつ何時より大きないのち(神や自然)に自らを取られたしても仕方がない存在です。その意味で、ガイアの子として生きるということは、生の根本にある残酷な暴力性にひもづく負い目を償うその日まで、“鎖”につながれたしもべ(奴隷)としての本性を持つということでもあり、ケイローンが弓を引き絞って矢を放つのは、こうした蠍座の鎖に対して楔を打ち込み、鎖に縛られたしがらみの家から脱け出して、再び自由を手にするためでもあった訳です。刑務所からの脱獄にも近いその試みは、いかにして成就しえたのでしょうか。
神話によれば、神の血を引く不死のケイローンはあるとき流れ矢により傷を負ったが、癒しの術に長けた彼をもってしても、この傷だけは癒すことができなかったため、その苦しみは永遠に続くかと思われたとあります。そこで、彼は自らに備わった不死身の能力を神(ゼウス)に頼んで他の人間へと譲り、死を迎えることができたと(その死を惜しんだゼウスによってケイローンは星に上げられた)。この場合の“癒せぬ矢傷”とは、おそらくガイアのしもべとしての本性や、そうである限り決して逃れることのできない負い目(罪悪感)のことでしょう。そうだとすれば、事故(偶然)とは言え、傷は負うべくして負った、いつかは必ずくるもの(必然)なのだとも言えます。
ただし、この下りで最も留意しておかなければならないのは、彼は単に矢傷を癒すことができなかったのではなく、むしろ苦しみを和らげるような一切の慰めを拒否し、しりぞけたのではないかという点です。感じる苦しみが深ければ深いほど、当の事態を不幸として慰め(られ)る行為というのは、逆に幸福への期待や執着を助長させ、恨みや憎しみ、苦々しさを生じさせてしまいます。その意味で、対症療法としての慰めは、ちょうどいかなる容器にも同時に二種類の純然たる液体を容れることができないように、苦しみを一時的に薄めることはできたとしても、決して消すことはできません。現に極度の不幸に陥った人というのは、大抵の場合、かつての幸福な思い出でさえ堪えきれない。その結果、自らの過去さえ奪い取られる傍らで、幸せでない今が次々と積み重なっていき、やがて何かに期待することや、希望を抱くことすらしなくなってしまう。夢や希望など、最初からなかったんだと自分に言い聞かせるようになる。そうなれば、ただただ時をやり過ごすようになり、刑期を終える長い長い時間の中で、ひとは次第に壊れていってしまいます。
逆に言えば、苦悩の喪失、その完全なる滅却こそが真の慰めなのであって、他はすべて行き止まりに通じるニセモノなのだとも言えます。したがって、苦しみやその原因である執着から逃れきるためには、ヨブ記のヨブ的な絶望のどん底、すなわち執着が向かっていき、思わず想像力が働いてしまうような全てのニセモノがもぎ取られた、ある種の内面的な真空状態が一時的にしろ作り出される必要があります(仏教的な意味での“諦め”にも近いですね)。だからこそ、ケイローンは自らの尊さの象徴でもある不死身の神性を捨てることで、決定的に容器(肉体)を空しくし、そこから離れ去ろうとしました。その行為は、いったん引き受けた負い目をとことん受け入れ、あきらかにしてみせた上でゆるすため(偶然の必然化=運命愛)でもあったはず。それは、先の「ただ漫然と時をやり過ごして、刑期を終えるのを待つ」という態度や通常の意味での“あきらめ”などとは真逆のものであり、しがらみは抜けられる、希望は抱けるという思いを持ち続けるだけの大変な勇気さえ伴うでしょう。
そうやって、自分が堕ちているのか、昇っているのか、その判別さえも希薄化し、ついに最後の一滴まで容器が空になったそのとき、自己消滅の極みとしての真空状態は訪れます。と同時に、ガイアとの固い紐帯は役目を終えて切り離され、その最後の息とともに魂(プシュケー)が吐き出される。それは空の容器をたちまち包み充たすだけでは飽き足らず、周囲へと漏れ出て、しがらみの外へ外へと際限なく広がっていきます(ギリシャ語のプシュケーと同系統のプシュケインには「息を吐く」という意味がありますが、と同時にプシュケーには蛹からかえり、ひらひらと宙を舞う「蝶」という意味もありました)。
ガイアの子でも「人」でさえもなくなった“それ”は、もはや「使役される奴隷」でも「誰かの魂」でもなく(むろん“私”の魂でも)、語るとすれば「魂であるところの私」という形でしか言い表せない何かとなっている。ここでしているのは、私たち人間にとってもっとも強固でかつ根深い思い込みである、実体という概念の死についての話です。つまり、肉体の中に何か精妙な「中身」のようなものとして魂が混入されているのではなく、あくまで魂という巨大な生の領域がまずあり、その一端を占める形で肉体というより狭い囲いが存在していたんだということへの気付きこそが、射手座の始まりであり、その本質にある発想なんです(あるいは、肉体は中にあるものを排出する空のふいご、ないし真空を得るためのポンプでもあるという捉え方)。振り返ってみれば、射手座が生来積み上げてしまう「哲学の塔」というのも、立派な見識や規範を社会に示す権威としての象牙の塔などではなかった。それはあくまで生きていく上でごく自然に身に着ける思い込みや、“私”は単なる一個の肉体でしかないという人として背負わざるを得ない限界から脱獄するための道具であり、迷いや苦しみを生み出し自らを壊してしまう脳味噌を、内部から撹乱・脱臼・粉砕し、その「外」へ踏み越えていくための台でもありました。そうした踏み台からの跳躍(メタ認知)を通じ、これまでとは全く異なる未知の感覚形式(=三番目の火)へと飛び込んでいくことで、意識は新たな領域=射手座以降の星座へと扉をあけていくこととなります。
君いま羅網に在るに、何を以て羽翼有るや
いのちの深みにおいて見出される、生が罪に前払いされて在るという事実、その矛盾(ねじれ)と苦しみの表象としての鎖と、自分も含めたすべての現象には実体があるという考え方の限界をとことん見つめ、素直に受け入れること。それが、蠍座の内奥にある此彼の区別を無効化してしまう位相の、更にその奥へと広がっている不可視の位相(巨大な生としての魂の領域)を開くための通過儀礼であり、3番目の火の領域の先頭を務める脱獄囚・射手座の世界の始まりでした(そういえば、仏陀は決して死後のことを語りませんでしたが、射手座は逆にあまり前を語りたがりませんね)。
火はもっとも軽く、精妙で、純粋さと浄化の象徴でもある元素です。蠍座の世界からの脱獄に際し、炎に包まれ跡形もなく燃え尽きた容器=身体は、烽火(のろし)となってガイアの手許から浮かび上がり、やがて重力の鉄鎖からも解き放たれて、この世の架空のしがらみは遥か彼方、豆粒のごとく極小化していきます(深みから広大さへ)。次第に、足元にはこれまでの大地に代わり、ぼんやりと青白い銀河が広がっていく。その視界はまるで宇宙飛行士。目に映るはもはや個々の人間ではなく、暗闇に灯る大小の光や点やそれらが織り成す模様のみ。辺りに見える在りとしあるすべてのものが宇宙の塵であり、聞こえるのはそれらが渦巻く銀河生起の息の音。しがらみを踏み越え、死を通過し、もう随分遠くまできたけれど、さりとて無に帰った訳でもなし。どこか、宮沢賢治が十代の頃に詠んだ「なつかしき地球はいづこいまははや/ふせど仰げどありかもわからず」という歌を連想させるような宇宙的孤独の背中を抱えつつ、射手座はここから先、何を見つめ、どこへ向かっていくのでしょうか。あるいは、どうして、何を以って、射手座は天まで来たのか。
神でもなければ人でもない、中間的異形者としてのプシュケー=魂(玉し火)となって、広大無辺の宇宙空間を漂う射手座の目。既にそれ自身がひとつの星であり、同時に夜空に浮かぶ数々の星々や、地上の明かりを眺めつつある訳ですが、そうしていると、次第に自分が空から見下ろしているのか、あるいは地上から見上げているのか、よく分からなくなってくる。厳密に言えば、それこそ有機交流電燈のように、カチリカチリと視点が切り替わりはじめ、そのうち明滅する一群の焔(ほのお)だけがそこに見えてくるんです。そして、そんな一瞬たりとも静止することのない光景をじっーと眺めていくと、この火という現象がじつに不思議な在り方をしていることにも、改めて気付かされてくる。
決まった形を持たず、たえず流動しているという点では川や海などの水と似ているものの、火の場合、さらに徹底して、いかなる固定的な実体も持っていません。つまり形も実体もなく、在るのはただただ燃焼現象のみ。そしてその燃焼現場では、明々と点火し、ある広がりを持って燃え上がる動きと、刻一刻と自らを使い尽くし、崩落して消え去らんとする動きが、同時進行で起こっている。一定時間もえて、また消えるというサイクル的循環ではなく、文字通り、生起と消滅が同時に在るんです。すべてを原因と結果で考えがちな世の常識からは明らかに外れている、こうした火の存在様式について、古代ギリシャのヘラクレイトスは「宇宙(コスモス)は火」という有名な言葉の他に、「反対のものが協調する。異なったもの同士から、最も美しい調和が生まれる。万物は抗争によって生じるのだ。」といった言葉で説いています。つまり、燃え上がるAという動きと、消え去る非Aという動きの絶えざるぶつかりあいが成立してこそ、それは正しく火であるということ。また、「自然」を貫き脈動する、逆向きに働きあう二つの流れが激しく拮抗している何らかの場こそが、魂(プシュケー)から見える森羅万象ほんらいの姿であり、そこでは世界を包む大炎を咲かすための「矛盾の一致」こそが正義と必然なのだということ。重力から自由になって、ラジカルな自己変容(眼差しの透明化)を経た射手座に、だんだんとそうしたことが見えてきたとき、自然と魂には翼がはえて(あるいは翼が広がって)、己の欲するところへ翔け行きたいというエロス的願望が強烈に芽生えることになります。魂というのは、どうしたって羽翼を持たずにはいられないんですね。
魂なんていうと誤解するかも知れませんが、射手座というのは魚座と違って、決して神秘的なサインという訳ではありません。彼らはただ、こうした止むに止まれぬエロス的願望ないし理想を胸に抱いているだけ。ただし、エロス(結合への衝動)とは言っても、射手座の場合、それは牡羊座や獅子座といった他の火の星座のように、個人的なものでもないんです。というのも、射手座は自己という火が、ただ在るだけで既に世界という大炎の一部であり、努力して参加したり構成などしなくても、人間である以上、「孤立している」ということなど在りえないということがよく分かっているからです。
つまり魂として見るということは、簡単に言えば何事も個人的には受け止めないということでもあり、これが射手座の特徴である他人への寛容さと自己への忠実さにも繋がっているんですね。そしてだからこそ、射手座は火を、エゴそのものを洗練・純化し、魂から見える光景を思い出し再現するために使うことができる。それは、天上の火を地上にもたらすということでもあり、一度は自ら断ち切った生の根本に潜むつながりの内にある矛盾を、今度はつながった人々ごと昇華し、統合してみせようという、無謀とも思える試みと言えます。
そういう意味では、平和の祭典であるオリンピックが、近代において開催されて以降、「いかなる差別をも伴うことなく、友情、連帯、フェアプレーの精神をもって相互に理解しあうことで、よりよい世界にすることへ貢献する」という理想を掲げつつも、常にテロの標的や政治利用の対象にされてきたことは、そのまま射手座のチャレンジの困難さや、多分に矛盾を孕んだケイローンの姿を表しているようにも思えてしまいます。けれどそれでも、文化英雄プロメテウスが神々から盗んで人類へ伝えたとされる聖火を運ぶランナーは、今後も、大勢の人の心に火をつけ、大炎を燃え盛らせるだろう聖火台へと走り、そこへ理想の火を投じ続けるでしょう。彼らが投じる火がなければ、世界は今よりずっと暗く気の滅入るものになってしまうはず。私たちにはどんな形であれ、人生はこんなにも素晴らしいことが起こりえるんだという光景を目にする機会が必要であり、それこそが射手座が人に与えることのできる最大の贈り物なんです。
また、射手座は木星によって支配される星座でもありますが、この木星は球もしくは丸い形で象徴され、「そこから世界が作られる想像力の種子」(フィチーノ)のようなものだともされています。かの「地球は青かった」ではないですが、射手座の聖火というのは、宇宙飛行士の目から見た、光差すガイアの姿なのだとも言えますね。
哲学的であるということは、物事を魂の視点を借りて見ることができるということ(厳密にはそこに論理性への偏愛が加わると思いますが)。楽観的であるということは、掲げた希望を、決して諦めずに持ち続けるということ。願わくば、一見異質な二つの特質を結びつける者として、射手座にはこの世界にいて欲しい、そんな風に思います。
射手座のKeyword:
根深い思い込みからの脱獄―実体の概念の死
その克服としての仏教的諦め―真空状態―運命愛
「魂であるところの私」/魂という巨大な生の領域がまずあり、その一端を占める形で
肉体というより狭い囲いが存在しているという発想
宇宙的孤独の背中(宮沢賢治)/中間的異形者としてのプシュケー
羽翼もちたる者―重力からの自由&エロス的願望
火の存在様式―矛盾の一致/自身がひとつの焔であると同時に、世界に大炎を咲かす役割を担う
エゴの洗練・純化―無謀さを伴うチャレンジ
オリンピック精神とその歴史―プロメテウスの聖火
「そこから世界が作られる想像力の種子」をもたらす
聖火ランナーとしての役目、哲学性と楽観性、異質混淆の姿
 Sugar(シュガー)
Sugar(シュガー)
1983年7月31日生。慶應義塾大学哲学科卒業後、ベンチャー企業の営業職を経て、より多くの人に占星術の面白さを伝えるべく、占い師の道へ。現在、対面鑑定・講座・執筆などを中心に活動中。男性占い師ユニットNOT FOR SALEメンバー。
WEB Site “astro-ragus” http://astro-ragus.com/