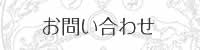星の見晴らし
こちらのコーナーでは 毎月の星の動き・星座のコラム、エンジェルメッセージをUPしてまいります。
星の動き・星座のコラムは 男性占い師ユニットNOT FOR SALEメンバーのSugarさんに、エンジェルメッセージはドリーン・バーチュー博士公認エンジェルセラピー・プラクティショナーⓇのMomokoさんに毎月更新していただく予定です。 お楽しみに!
【星の見晴らし 土星がもたらしてくれるもの】
NOT FOR SALE Sugar
10月6日、約3年ぶりに土星が星座を変え、天秤座から蠍座へと移りました。
既にさまざまな方が蠍座土星の意味について触れていますので、そこの解釈については他の記事にお任せするとして、本エントリーでは主に「土星がもたらす経験プロセスとはどういうものなのか?」という点について改めて掘り下げていきたいと思います。
■孤独者の作業としての土星経験
毎年雑誌などでこぞって取り上げられ、話題にのぼる“幸運をもたらす”木星に比べ、土星は古来より悪いことや災いなど、“不運をもたらす”最大の凶星として、人々から恐れられてきました。いわく、土星は人生に停滞をもたらし、苦痛を余儀なくされる“牢獄”そのもので、と同時にそこへ人を押し込んでは見張っている監視者である。あるいは、土星と関わるタイミングというのはすべからく苦痛な「服役」を告げるものであり、できれば避けてしまいたい不幸な時期であると。
しかし、土星が司るのは、そうした重苦しく陰鬱な経験だけではありません。例えば、土星と同一視されるローマの農業神サトゥルヌスは、いつも収穫のための鎌を携えた老人の姿で描写されてきましたが、彼は未開の蛮族に農業とぶどうの木の剪定を教えた偉大な教師であり、自身が祭神であり後のクリスマスの原型ともなったサートゥルナーリア祭では、奴隷にも無礼講を許すなど、人々に豊かな秩序を与える慈悲深い守護者でもありました。
もっとも有益な教訓を与えてくれる存在であると同時に、耐え難い苦痛を感じさせられる相手でもあるという矛盾。そのどちらか一方ではなく、両方ともが土星であるということを十分に理解することができたとき、私たちは初めて土星と親しくなっていきます。そのプロセスは、錬金術においてもっとも粗雑で未知な「黒よりも黒い」状態にある第一原質ないし「鉛Saturn(=土星)」の中に埋もれた黄金を見出し、長く忍耐強い作業を通じてそれを抽出せんとした、錬金術師の孤独な試みに重ねることができるでしょう。
卑金属を金に変容させる術としての錬金術は、何よりもまず重く沈み込むような「黒い土」の探求から始まりました。この黒い土は身のまわりのいたるところに偏在し、私たちを取り巻く「有限」の象徴であり、また作業をおこなう錬金術師本人とも見做されます。つまり、人は他者から切り離された孤独者となったとき、図らずも錬金術師となりて、自分自身の中にあって自らを閉じ込め、闇に包まれつつも確として存在している“何か”に初めて目を向けるようになるんですね。それはどういう体験なのか?以下、少し詳しく土星的な経験について見ていきたいと思います。
■土星がもたらす二つの感情
土星は有限の象徴であり本人の一部でもあると謎かけのような表現をしましたが、もっと平易な言い方でいえば、土星は私たちの中にある「常識」だと言うことができます。常識とは、暗黙の慣習であり、自明なルール。あるいは、自分の中での「当たり前のこと」、誰もがそう思っているはずだと思えるような事柄のことですね。地球は丸く、太陽は東から昇って西に沈み、原発をやめられないのも「経済のため」には仕方なく、人は自分の意志で人生を生きている、などなど。
それらはすべて「当たり前のこと」であるがゆえに、なぜそのことが当たり前なのかということについて私たちは改めて考えてみる機会がなく、だからこそ常識は意識の盲点(黒い土)ともなりやすいんです。実際、私たちがいかに多くの「当たり前」を自分で点検することなしに日々を過ごしているか、考え始めるときりがありません。地球は本当に丸いのか、その「根拠」を一度だって自分で確かめたことがある人がどれだけいるでしょうか。そうしたほとんどの「当たり前」を、私たちはいわば無意識裡にスルーしてしまっている訳ですが、そうであるにも関わらず、たえず私たちはそうしたあやふやな思考が作り出したリアリティーの中で生きています。例えば「死ぬって何?」ということを私たちはみな知っている気がするし、それは「生きる」ということとセットの事柄としてぼんやりと頭の中に浮かんでくるでしょう。
そうした死の表象は、しばしば人に不安や恐怖といったネガティブな感情を惹き起こします。ただよく考えてみると、「死ぬ」という言葉から表象されるのはあくまで他人の死体、他人の死であって、さまざまな負の感情が生じている時というのは、それら他人の死と自分の死がごっちゃになっているだけなのだということが分かってきます。
じつは、どう考えていっても、自分の死というのは考えられません。なぜなら世界のどこにも「自分の死」は存在しないから。ないんです。どんなにくまなく探っていっても、生きているということしか見当たらない。やがて、これまで無自覚に「生きる」と「死ぬ」をセットにしていた「当たり前」というのは本当は間違いで、死ぬことは生きることとセットなんかではなく、実際には生きていること、いや存在していることしかない、ということに気が付いていく。とは言え、これはただのいい間違いや手違いの修正とは訳が違います。もし一度ここで間違いを認めてしまえば、今までこの思い違いのおかげで、見ず、考えず、行動せずに済んできた、「生きる」ということの“その先”を、ひとり自分の目でみにいかなければならなくなる。
間違って思い込まれてきた常識自体が、すでに生きた体験である以上、体験された「誤謬」もすでに現実の一部であり、それは自分がこのまま動かず、あやふやなリアリティーの中に居続けることで得られる安寧を約束してくれるものでさえあります。そうなれば完全に状況依存ですね。裏を返せば、これまで現実だと思い込んできたリアリティーの「外」へ出るというのは、それだけ骨が折れる、大変なことだと言うこと。
結局、ありもしないことを怖がったり疑ったりして誤謬に身を委ねている方が、本当のところ自分は何も分かっていないし、無力なのだということをきちんと認めるより、ずっと楽なんですね。それゆえ、どこかで「常識」や「当たり前」の過ちに気付いたとしても、自分自身が誤謬そのものであるかのように感じられてしまい、実際にはなかなかそれを正せない、選択できないといったことがしばしば起きてくる。こうした事態は、今すでにある自分は変える必要がない、それくらい自分を大事なものだと思いたがる人間の欲求がいかに強固なものであるかをよく物語っています。
このように土星というのは、思い込みを利用した罠を通じ、人のいびつな自己愛を正確にはかって告発してくる訳ですが、そうしてメランコリーの深部へと沈み込んでいくと、一方で別の奇妙な感情が湧いてくるのも感じられるでしょう。当初の「死とは何か」という問いは、「生きるとは何か」を経て、いつの間にか「生きて存在しているとはどういうことか」という問いへと変わってきました。ここまでくると、もう日々の生活の中での死をめぐる個別的なストーリーではなく、存在と無をめぐる宇宙的なからくりの話がひとつの構造として感じられてきます。たとえば「自分は自分の意志で人生を生きているんじゃない、なぜだか分からないけれど、存在という形式の中で生かされてあるんだ」といった風に。するとそこで、視点がくるんと反転していくんです。
土星の告発により浮上してきた、分かったふりをしていた自分の姿、そしてそんな自分の姿を見ないようにしていただけだった自己愛など、自分やリアリティーにまつわるあれこれが、単に存在形式の「中身」ないし「内容」として見えてくる。やがて、少しずつ自分の望む形で自分を見たいという願望に惑わされることがなくなっていき、そもそも内容や中身のことであれこれ悩むのはお門違いで、本当の問題は形式の側にあるのかもしれないと、ふっと気持ちが開けていくんです。その瞬間、ある種の至福感というといいすぎかもしれませんが、そういう感情が湧いてきて、メランコリーが癒され、救われていくんですね。
■謎の感覚
こうして土星は、人間の中に潜む誤謬や奴隷根性を炙り出し、無力感にあえぐメランコリーへと誘い込んでいく一方で、時が熟すと、サートゥルナーリア祭のような祝祭感情を湧かせることでそれまでのメランコリーをかき消し、「形式の謎」を味わうというモード(謎の感覚)へと人を導いていく。
この謎の感覚へスイッチが入ると、周囲の見え方や日常風景が変わってきます。例えば、親しい人が死んでしまうとか、仕事を失う、恋人と別れるといった、それこそ以前ならこの世の終わりとばかりに落ち込み、メランコリックになっていたであろう出来事に対しても、むしろそれを味わうとか、面白がるといった構えに変わってくる。なぜだか分からないけれど、生きて存在しているという絶対的な謎を前提にしていると、色々なことが不思議に思えてくるんです。
それはどうしようもない分からなさの前で途方に暮れる、ということでもあります。理解を超えた形式を、自分は既に生きているのだから、その内容である現象=人生というのは本当に何が起こるか分からない。そこでは何でもありだし、何でもしていいんだいう風に、腹が据わってくる。非常に逆説的ですが、私たちは逃れえない形式を生きているという自らの限界を受け入れることで、かえって自由になっていく訳です。これが自分だと思い込んでいる自分は実は間違いでしかないですし、どこまで先に行っても自分のことは分からない。それでも、生きて存在していることだけは相変わらずで、そういう意味では「私たちは夢と同じものでできている」というシェイクスピアの言葉も、言葉のあやなどではなく、構造上、形式上の事実なんです。
土星のもたらす2つの感情の中で引き出されていく謎の感覚は、そういう夢でしかない現実を夢と自覚した上で見ていくことを教えてくれる。夢の中で目覚めていられるだけの意識の冴えをもたらしてくれるんですね。おそらく、これこそが人類の教師サトゥルヌスがもたらす恩恵であり、錬金術師が黒い土(土星)の中に見出す黄金なのでしょう。